以下の文章はとあるアルバムの批評ですが、ジャンルや作家などの情報を伏字にしアルバムを特定できないようにしています。
どこの国のどんな音楽か。そもそも存在する音楽なのか?想像しながらお楽しみください。
正直なところ、私はそんなに《◆◆◆》が好きではない。先鋭的な音楽家も少なくないが結局のところジャンル自体が大衆性に支えられたものであり、故にその表現手法にも限界がある。実際の所《◆◆◆》は《◆◆◆》のようなものばかりではないか……その固定観念を鮮やかに裏切ってくれたのが本作である。
《◆◆◆》、《◆◆◆》、《◆◆◆》など多数の手を介してリスナーに届けられる大衆音楽の大きな落とし穴は、往々にしてリスナーの生活感覚をないがしろにしてしまう点である。大衆音楽で語られる「大衆」は概して、多くの人の経験や価値観の共通部分を取ったような、架空のものである。架空の友情、架空の恋愛、架空の青春……人々はこの架空性・普遍性故にそこにイデア性=《◆◆◆》性を見て、「推し」とするのかもしれない。しかし私は「あなたの表現する世界は本当の感情に結びついてるのか?」という思いが先行してしまう。そして”大衆”からどんどん外れていくのである。
音楽好きの間で《◆◆◆》をはじめとした《◆◆◆》が流行っているのも、ある種冷めた目で見ていた。確かに出音としては音楽ファンの琴線に触れるものがあるかもしれない。だが結局それは「そういうファン層に向けたマーケティング」に外ならず、「《◆◆◆》らしさ」の逸脱や拡張には至っていない、とも感じてしまうのである。
故に、《◆◆◆》からの大いなる逸脱といえそうなこのアルバムには腰を抜かした。演者である《◆◆◆》はかの《◆◆◆》のメンバーとして知られる。そう聞いた私はこのアルバムもその流れに立脚した「大衆」音楽なのだろうと思いこんでいたが、《◆◆◆》の流れを汲んだ内省的な内容である。
白眉と言えるのは《◆◆◆》だろう。曖昧な《◆◆◆》を繰り返す《◆◆◆》、踊ることを全く想定していない特殊な《◆◆◆》、《◆◆◆》風の《◆◆◆》。従来の《◆◆◆》にはありえなかった土の匂いがする楽曲であり、極めて私的である。
このアルバムは全体的に派手な演出を抑え、内省的な空気感が漂う。《◆◆◆》の手法を使い人々の生活と同じ視点からみることで、巨大な産業構造をバックにしていた従来型の《◆◆◆》では表現できなかった世界観を構築している。手法が目的になっていないのも、評価すべき点である。
このアルバムをどのように捉えるかが今後の《◆◆◆》全体の問題になってくる。《◆◆◆》や《◆◆◆》≒《◆◆◆》のような過去の例を振り返れば、単なる産業音楽を越えた存在になるためにはこのような私的な視点を積極的に取り入れた製作が重要になってくるだろう。
この文章は外部に公開される批評でありながら、極めて閉じたものです。なぜなら批評対象は私しか知りえないからです。
この文章は名前が出ていない以上音楽の広告や宣伝ではありませんし、音楽の知名度にかこつけた売名でもありません。私がこの作品を聴いて、表現したかったから書いた文章です。故にこの批評は、最も純粋な批評といえるでしょう。
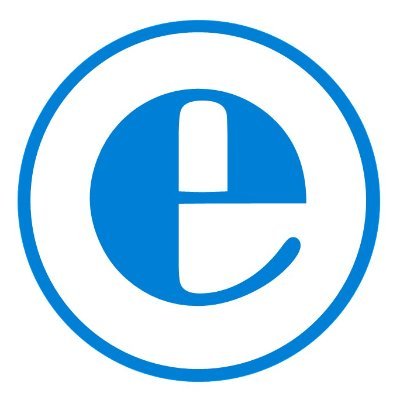
Water Walk編集長。2019年からネット記事に影響を受けた音楽ブログを執筆し、カルト的に話題に。2022年からは知人ライター達とnote上でWater Walkを設立。ここ数年は前衛音楽などの現代芸術を手本にした批評を制作、前衛的批評”クリティシスム”を提唱している。Sound Rotaryへの寄稿、KAOMOZINE編集など、外部でも精力的に活動中。
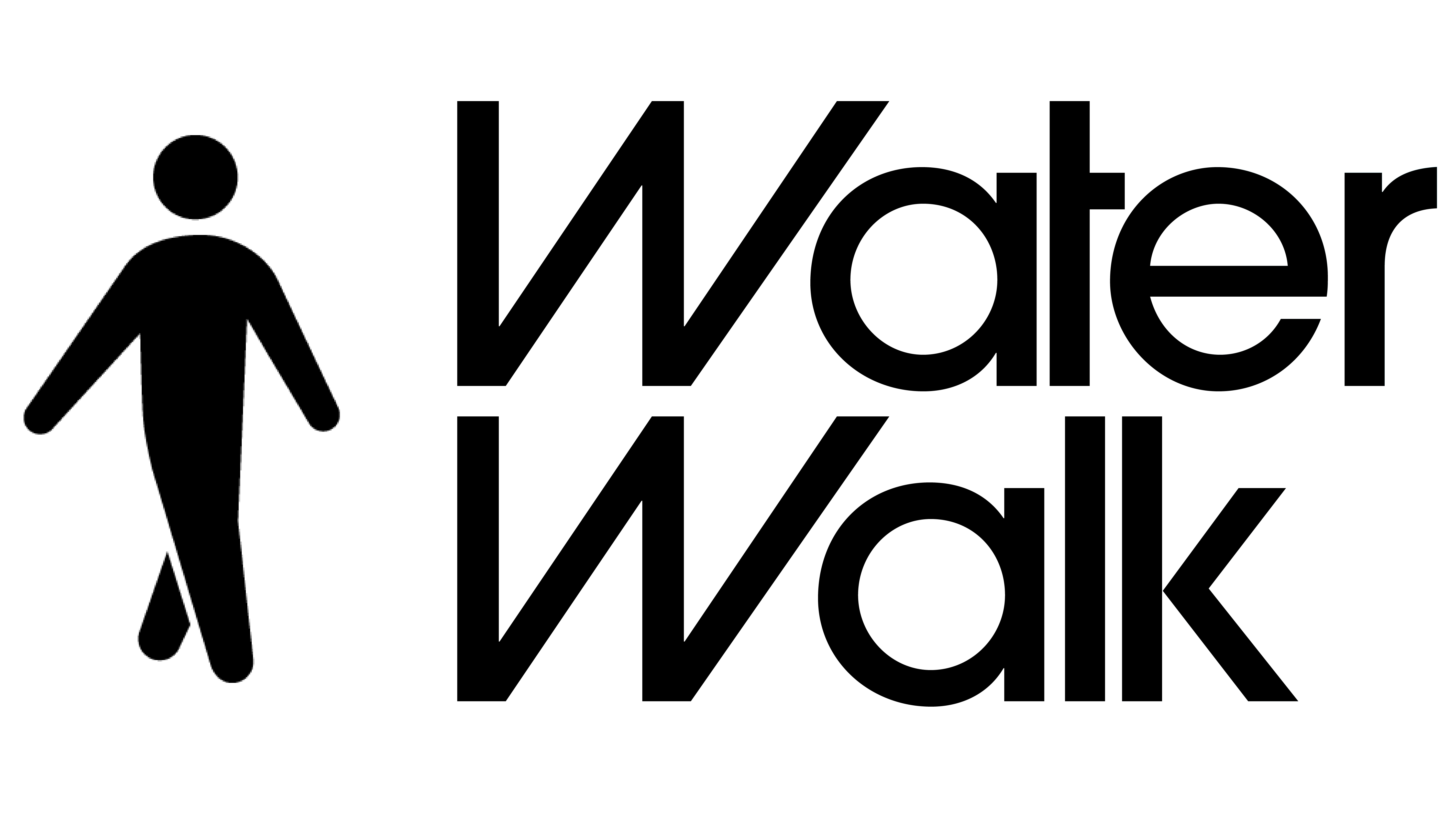
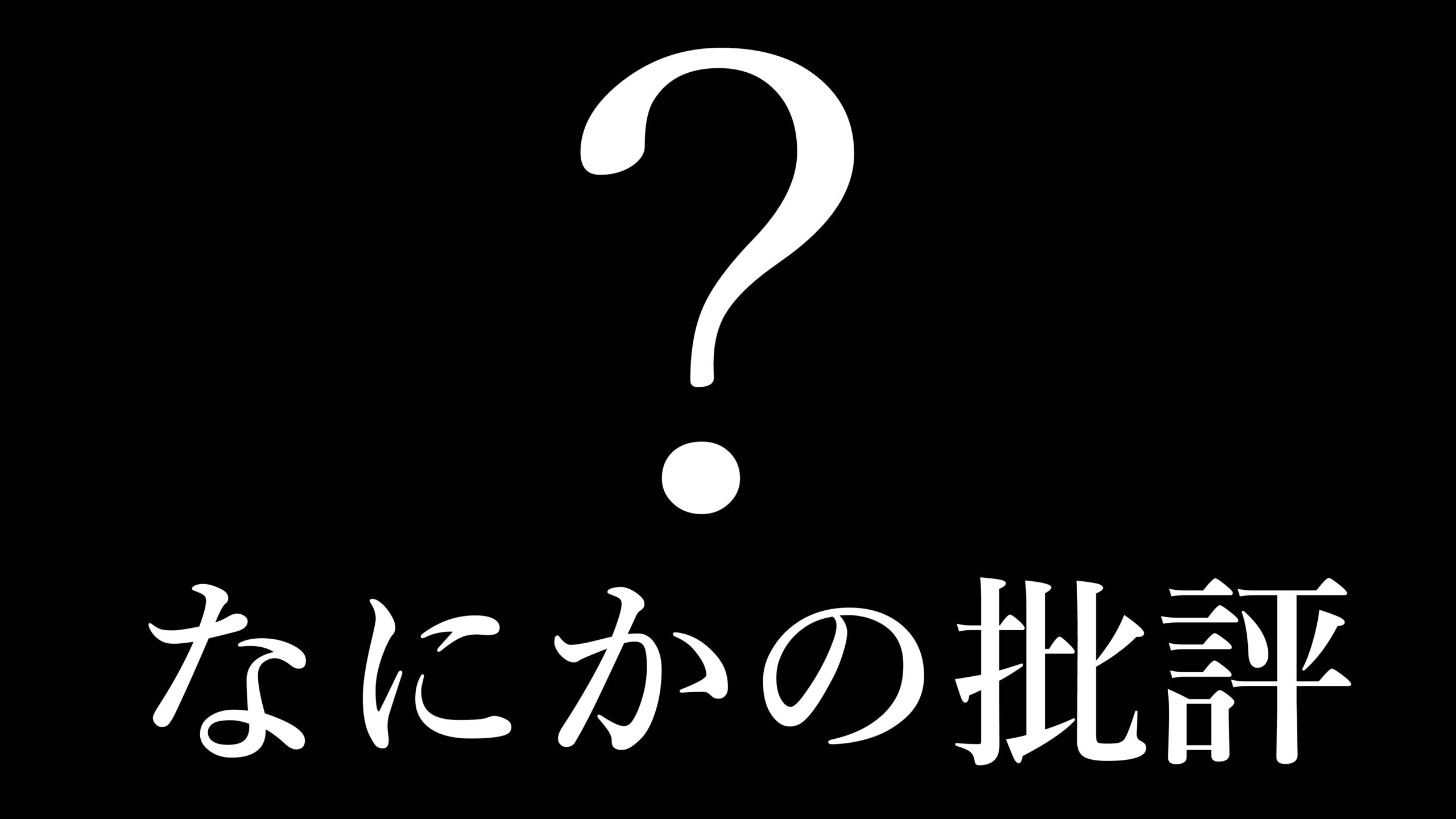
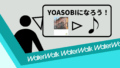

コメント